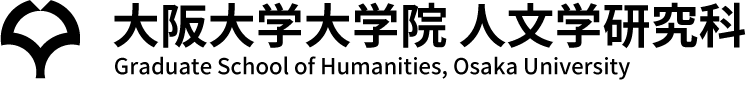この専門分野では、中国の思想や文化事象を対象に、文献学的脈絡にもとづいた歴史的研究が行われています。しかし中国哲学はそれ自体、単なる「史」にとどまらない、時代や地域を越えて響く普遍的な問いをはらんでいます。そもそも思想史という枠組みは、そうした問いへの入口であり、一見歴史をたどる営みに見えながら、実は存在や意味の根本を問う形而上学的思索へと開かれているのです。
哲学・思想・宗教・政治・文化・科学・神話・思想交渉──どこから出発してもかまいません。入り口は人それぞれでも、問いを真に深めていけば、それらは必ず根源的なところで交わり、つながっていきます。大切なのは、自分の関心に正直であること。いま手の届く問いに誠実に向き合い、足元を固めながら、意識の片隅に意味世界を忘れないこと。その積み重ねが、やがて大きな構想に育ち、ばらばらに見えていた問いが、あるときふと意味を湛えた風景となって立ち上がってくるはずです。
その、静かに心を震わせる風景に出会ってみたい方を、お待ちしています。
教員紹介
教授 辛賢
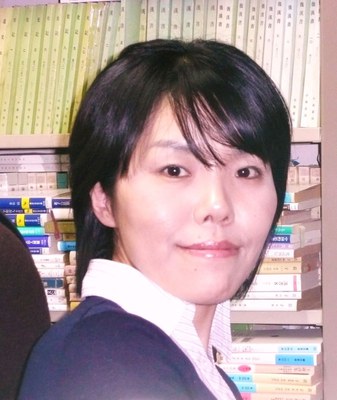 しん ひょん しん ひょん1967年、韓国ソウル生。2002年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術振興会外国人特別研究員(筑波大学)、2004年大阪大学大学院文学研究科講師、2022年4月より大阪大学大学院人文学研究科講師を経て、2023年9月より現職。 専攻:中国哲学、漢代易学 |
- 研究紹介
- 漢・唐代から宋代における易学・術数学関連の文献を調査し、その思想史的展開について研究を行っている。漢易の術数理論が、漢代以降、どのように受容されていったのか、とりわけ、新たな易学、いわば義理易が開かれる唐宋両代における漢易術数の波及、その様相について考察を行っている。漢易の「数」と「象」は、漢代的な論理展開の技術・手段に止まらず、それ自体が哲学的概念、思索の対象として進められていったが、その解釈学的変遷、特に宋代の学問形成に及ぼした影響について主な関心をもっている。
- メッセージ
- 近代以降、西洋の学術や文化の流入により、私たちはそれまでの儒教の権威の枠組から自由な価値判断ができるようになりました。しかし、これはそれまで長い間培われてきた儒教の伝統から脱却したことを意味するものではありません。むしろ、20世紀以降、西洋の新しい価値観の流入は、受ける側の伝統的思想の上に変容をもたらし、全く新しいものを生み出していることさえありうるからです。今日を生きる我々にとって中国古典研究のもつ意味はなにか、この問題について皆さんとともに悩み続けていきたいと思います。
- 主要業績
- 『漢易術数論研究―馬王堆から『太玄』まで―』(汲古書院、2002年);「『太玄』の「首」と「賛」について」(『日本中国学会報』第52集、2000年);「後漢易学の終章―鄭玄易学を中心に」(『東方学』第107輯、2004年);「易緯における世軌と『京氏易伝』」(共著『両漢における易と礼』汲古書院、2006年);「象」の淵源―「言」と「意」の狭間―」(『大阪大学大学院文学研究科紀要』第48巻、2008年); 「王弼忘象論再考」(共著『両漢儒教の新研究』汲古書院、2008年)
- 概説・一般書
- 「三国時代の思想―言語観の射程―」(『創文』496、創文社、2007年);『三国志論集』(共著、汲古書院、2008年);『知のユーラシア』(共著、明治書院、2011年)
2025年 7月更新