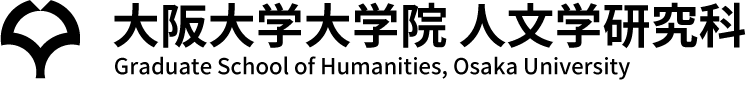考古学講座は、開設が1988年と比較的新しいものの、それ以前の国史研究室時代からの研究・教育の蓄積があります。専任教員は高橋照彦教授、中久保辰夫准教授の2名です。日本考古学に重点をおいた研究・教育を行っていますが、教員や大学院生は海外のフィールド調査をも手がけて、比較考古学的な幅広い視点を探求しています。
研究室では、毎年実施する発掘などのフィールド調査とその資料整理を基礎とした教育を重視するとともに、とくに大学院では考古学や人文科学の方法論の討論にも力を入れ、国際的視野にたって日本考古学を推進しうる研究者の養成に努めています。
人文学研究科のなかでは歴史の浅い研究室ですが、この研究室で研鑽を積んだ多くの修了生は、すでに各地の大学、研究所、教育委員会、博物館などに勤務し、考古学研究の第一線に立って活躍しています。
研究室の活動・講義内容をはじめ詳しい情報は、ホームページに掲載していますので、ぜひたずねてみてください。
教員紹介
教授 高橋照彦
 たかはし てるひこ たかはし てるひこ1966年生。1992年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退。博士(文学)(京都大学、2014年)。国立歴史民俗博物館考古研究部助手、奈良国立博物館学芸課研究員を経て、2002年大阪大学大学院文学研究科助教授、2007年同准教授、2015年より現職。 専攻:日本考古学、東アジア考古学。 |
- 研究紹介
- 「歴史考古学」と通称される分野、日本で言うと、飛鳥・奈良時代以降の考古学を主に専門としています。これまで、日本古代のやきものである三彩・緑釉陶器や銭貨といった考古資料を通して、奈良・平安時代の文化や社会を明らかにしようとしてきました。そのほかにも、古代寺院や古代墳墓などについても、現在研究を進めています。発掘調査の関係では、平安時代の須恵器や緑釉陶器の窯である篠窯、中国新疆ウイグル自治区に所在するシルクロードのオアシス都市、ニヤ遺跡の日中共同調査などにも携わっています。
- メッセージ
- 大阪大学の考古学研究室は、例年、夏期のフィールド調査を続けています。その際に大学院生はまさに調査担当者として研究室を引っ張っていく存在であり、その実践的な取り組みは、考古学さらには社会における様々な能力を向上させる、良い機会になるはずです。他大学から進学した大学院生も少なくなく、学内外の学会・研究会も多いため、院生は切磋琢磨しながら研究を進めています。私自身は、考古資料と文献史料を統合した歴史像の構築が目標ですが、考古学の新たな未来を切り開く多くの人材を待ち望んでいます。
- 主要業績
- 「平安初期における鉛釉陶器生産の変質」『史林』77-6(1994年);「正倉院三彩の伝来過程と製作契機」『仏教芸術』259(2001年);「欽明陵と檜隈陵―大王陵最後の前方後円墳―」『待兼山考古学論集』(2005年);「銭貨と陶磁器からみた日中間交流」『シルクロード学研究』23(2005年);「律令期葬制の成立過程」『日本史研究』559号(2009年);「考古学からみた法華堂の創建と東大寺前身寺院」『論集東大寺法華堂の創建と教学』(2009年)
- 概説・一般書
- 『概説 中世の土器・陶磁器』真陽社(共著、1995年);『お金の不思議』山川出版社(共著、1998年);『改訂 日本古代史新講』梓出版社(共著、2004年);『列島の古代史 ひと・もの・こと』5、岩波書店(共著、2006年);『Jr.日本の歴史』①、小学館、(共著、2010年);『天平びとの華と祈り―謎の神雄寺―』柳原出版(共著、2010年);『天皇陵古墳を考える』学生社(共著、2012年);『野中古墳と「倭の五王」の時代』大阪大学出版会(共編著、2014年);『日本古代交流史入門』勉誠出版(共著、2017年)
2018年 8月更新
准教授 中久保辰夫
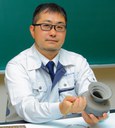 なかくぼたつお なかくぼたつお1983年3月生。2011年3月、大阪大学大学院文学研究科文化形態論博士後期課程修了。大阪大学埋蔵文化財調査室助教(2011年4月~2018年3月)、京都橘大学文学部歴史遺産学科准教授(2018年4月~2025年3月)を経て、現職。第9回日本考古学協会賞奨励賞受賞。 専攻:日本考古学(古墳時代)、比較考古学。 |
- 研究紹介
- ・日本古代の土器研究:土師器と須恵器を代表とする日本古代の土器様式について、世界各地の古代土器の特質と比較しつつ、調査をしています。
・古墳時代における対外交流と国家形成論:東アジア世界を駆け巡った渡来人・移住民に関わる考古資料に着目して、その歴史的役割を国家形成論の中で位置付けています。
・日本古代の食文化研究最新光学機器を用いて、土器にのこる調理痕跡の観察法を開拓し、古代食の復元、食が持つ文化的意義の解明を試みています。 - メッセージ
- 考古学の魅力は、発掘、長考、対話です。発掘は考古学の基本であり、自らの手で歴史文化の断片を掘り出すことは、何ものにも代え難い感動となります。阪大考古学研究室はフィールド教育に定評があるので、充実した研究環境となるでしょう。 そして、遺跡の地に立ち、数万年を超えるスケールで、人類文化の意味を掘り下げ、調査の意義を発掘仲間と長考する。さらに対話を通じて、文化遺産の魅力を地域や世界に発信し、次世代につなぐ。こうした魅力に惹かれた探求心旺盛な仲間を考古学研究室は求めています。
- 主要業績
- ・中久保辰夫2024「古墳時代の気候と渡来人の来着時期 」『季刊考古学 特集:高時間分解能古気候学の進展と考古学』168号、雄山閣
・中久保辰夫2021「近畿지역의 고대 백제계(韓系) 이주민의 연구」『百済研究』74号 忠南大学校百済研究所
・NAKAKUBO, Tatsuo. 2018. Excavating the Mounded Tombs of the Kofun Period of the Japanese Archipelago: A History of Research and Methods. Burial Mounds in Europe and Japan: Comparative and Contextual Perspectives. KNOPH, T, STEINHAUS, W, FUKUNAGA, S (eds.). Archaeopress.
・中久保辰夫2017『日本古代国家の形成過程と対外交流』大阪大学出版会
・福永伸哉, 高橋照彦, 中久保辰夫(編)2015『21世紀初頭における古墳時代歴史像の総括的提示とその国際発信 』大阪大学大学院文学研究科 - 概説・一般書
- ・中久保辰夫2023「2章 王権と手工業生産」『シリーズ地域の古代日本6 畿内と近国』吉村武彦,川尻秋生,松木武彦編、KADOKAWA 2023年1月25日 (ISBN: 9784047036970)
・中久保辰夫2022「先史・古代編第一章考古遺産が物語る北摂の先史時代」『新修摂津市史 第一巻 自然地理 先史・古代 中世』摂津市
・中久保辰夫2021「世界の墳墓と世界遺産」『文化財としての「陵墓」と世界遺産』陵墓限定公開40周年記念シンポジウム実行委員会、新泉社
・高橋照彦・中久保辰夫(編)2014『野中古墳と「倭の五王」の時代 』大阪大学大学院文学研究科
2025年 5月更新