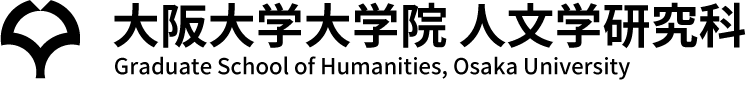この専門分野では、古代オリエント・地中海世界、中世・近代のヨーロッパ世界、また近代の南北アメリカやオセアニア、アジア、アフリカの植民地などヨーロッパ人の進出によって形成された諸世界の歴史を対象とするのですが、それらの歴史の中の諸現象を個別に考察するだけでなく、世界史の中に位置づけることを重視しています。院生の皆さんには自力で高度な研究を目指す自立心と、研究室共同体での相互批判から学ぶ開かれた精神が求められます。この専門分野では創設以来、多数の優れた研究者を送り出してきました。またここで学んだ後、西洋史研究以外の世界に進む人もいます。研究に困難はつきものですが、関心があるならば挑戦してみませんか。
教員紹介
教授 栗原麻子 教授 前川一郎 教授 Gerold Krozewski(兼) 准教授 中谷 惣 准教授 見瀬 悠
教授 栗原麻子
 くりはら あさこ くりはら あさこ1968年生。1995年、京都大学大学院文学研究科博士課程(西洋史学専攻)指導認定のうえ退学。博士(文学)(京都大学、1998年)。日本学術振興会特別研究員、奈良大学講師を経て、2004年10月より現職。 専攻:古代ギリシア史 |
- 研究紹介
- 私の専門は古代ギリシア社会史です。アテナイ民主制についての研究は、民会のような政治の場での男性市民の活躍に目を向けがちです。それにたいして、家族愛や友愛といった私的な絆に囲まれた個人の側から、ポリスの共同体性を問いなおし、アテナイ政治史を読み替えるのが、当面の目標です。より具体的には、復讐意識と共同体性の関係を、法の運用の場である民衆法廷での言説をターゲットにして探っています。
- メッセージ
- 歴史学は、古を知ることで現在を知る学問です。ひとつには、他文化を知ることで自己を反省するといった意味において。いまひとつには、我々を規定している西洋的な思考を、その源流から眺めるという意味において。古代ギリシア人の心の風景にできるだけ近づいて、彼らの声に耳を傾けてみませんか。
- 主要業績
- 「『思い出さない』誓いをめぐって 前403年アテナイにおける和解儀礼」『古代文化』62-1(2010);“Personal Enmity as a Motivation in Forensic Speeches”, in: Classical Quarterly, 53-2, 2003;「紀元前415年のアンドキデス」『西洋古典学研究』48巻(2000);「古典期アテナイにおけるフィリアと共同体」『史林』78-4(1995);「前4世紀アテナイの親族関係―イサイオスの法廷弁論を中心に」『史林』76-4(1993)。
- 概説・一般書
- 南川高志・山辺規子編『大学で学ぶ西洋史〔古代・中世〕』ミネルヴァ書房(共著、2006);奈良大学文学部世界遺産コース編『世界遺産と都市』風媒社(共著、2001);『歴史のなかのジェンダー』藤原書店(共著、2001);G・デュビィ,M・ペロー監修『女の歴史 Ⅰ古代1』藤原書店(共訳、2000);「獲得されるものとしての親族関係―前4世紀におけるソロンの遺言の法の運用をめぐって―」歴史学研究会編『地中海世界史 第5巻 社会的結合と民衆運動』青木
書店(共著、1999)。
2018年 8月更新
教授 前川一郎
 まえかわ いちろう まえかわ いちろう1969年生。創価大学大学院文学研究科単位取得退学。M.Phil. in History (Univ. of Birmingham). 博士(人文学)。日本学術振興会特別研究員、創価大学文学部助教授、同准教授、同教授、同大学国際教養学部教授、立命館大学グローバル教養学部教授を経て、2025年4月より現職。 専攻:ブリテン帝国史/歴史認識問題 |
- 研究紹介
- 近現代の帝国や植民地主義の歴史を、ブリテンを軸に研究しています。これまで、帝国主義や脱植民地化の時代を中心に、政治、経済、文化の面を問わず様々なテーマを、実証史学に照らして論じてきました。ずっとこだわり続けてきたのは、<帝国的な支配>とは何か、それは現代世界に何をもたらしたのか、といった問いであったような気がします。近年では、植民地主義の暴力や不正義の歴史を「問わないこと」で成り立ってきた、いわば<植民地主義忘却の近現代史>の問題を、「植民地責任」という視点から考えています。
- メッセージ
- グローバリゼーションは、自由や民主主義といった普遍的価値を世界に広めると共に、人類史上突出した暴力の歴史や、格差や差別に満ちた社会をひたすらに生みだしてきました。そうした陰の部分を置き去りにして、グローバルな発展ばかりに目を奪われていると、だんだんと偏った世界観に陥ってしまいます。グローバルな何かを論じるなら、同等かそれ以上に、そこで生じた矛盾に目を向けてみる。私の授業では、そんなあたりまえの世界史的センスを養い、そのうえではじめてグローバルな視点の豊かさを探求していきます。
- 主要業績
- “Cold War and Decolonisation: The British Response to Soviet Union Anti-colonialism in Sub-Saharan Africa,” The Journal of Imperial and Commonwealth History 51 (1): 182-210 (2023). “Neo-Colonialism Reconsidered: A Case Study of East Africa in the 1960s and 1970s,” The Journal of Imperial and Commonwealth History 43 (2): 317-341 (2015). 「アフリカからの撤退――イギリス開発援助政策の顚末」『国際政治』(173)15-27(2013年)。「イギリス植民地主義のあとさき――2001年ダーバン会議の教訓」『季刊戦争責任研究』(63)11-19(2009年)。「独立期アフリカにおける地域経済関係――東アフリカ共同体(EAC)の経験」(『アジアからみたグローバルヒストリー』所収、ミネルヴァ書房、2013年)。『イギリス帝国と南アフリカーー南アフリカ連邦の形成1899-1912』ミネルヴァ書房(単著、2006年)
- 概説・一般書
- 『歴史学入門――だれにでもひらかれた14講』昭和堂(編著、2023年)。『教養としての歴史問題』東洋経済新報社(編著、2020年)。『歴史教育「シン」入門――歴史総合から世界史探求・日本史探求へ』清水書院(共著、2025年)。『論点・東洋史学――アジア・アフリカへの問い158』ミネルヴァ書房(共著、2022年)。『よくわかるイギリス近現代史』ミネルヴァ書房(共著、2018年)。『イギリスの歴史【帝国の衝撃】イギリス中学校歴史教科書』明石書店(単訳、2012年)。
2025年 4月更新
准教授 中谷 惣
 なかや そう なかや そう1979年生。大阪市立大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、信州大学助教を経て、2018年4月より現職。 専攻:ヨーロッパ中世史(イタリア中世史) |
- 研究紹介
- イタリアの小さな町の文書館に所蔵されている、中世の法廷や議会の記録を読んでいます。そこには住民からの様々な訴え、たとえば貸した金を返せ、司祭から暴力を受けた、貧しいので刑罰を軽くしてほしい、公道の整備が必要だ、税金を安くしろ等が記されています。こうした市井の人びとによる都市国家への訴えを通じて、中世に特有の、しかし近代以降にも通じる要素をもつ、国家、正義、公共善が立ち現われてくる過程を研究しています。
- メッセージ
- 中世の裁判記録や契約文書、あるいは医者の覚書などの個人的な文書を読んでいると、時には思いもよらぬような、でも時にはとても共感できる、考えや行動に出くわす瞬間があります。うす暗い文書館で、遠く離れた時空間に生きた彼ら彼女らと通じ合えたような気がしたとき、何かとても満たされた気持ちになります。それが私の研究の原動力です。
- 主要業績
- 『訴える人びと―イタリア中世都市の司法と政治―』名古屋大学出版会(2016年);“The Gratia and the Expansion of Politics in Fourteenth-Century Lucca” The Southern African Journal of Medieval and Renaissance Studies 22/23 (2013).;“La giustizia civile a Lucca nella prima metà del XIV secolo” Archivio storico italiano 630 (2011).
- 概説・一般書
- 『はじめて学ぶイタリアの歴史と文化』ミネルヴァ書房(共著、2016年)
2019年 4月更新
准教授 見瀬 悠
 みせ はるか みせ はるか1985年生。2016年、東京大学大学院人文社会系研究科(西洋史学専攻)単位取得満期退学。博士(歴史学)(パリ=エスト大学、2021年)。日本学術振興会特別研究員、パリ=エスト大学博士課程契約研究員、2020年4月大阪大学文学研究科講師を経て、2023年1月より現職。 専攻:近世フランス史 |
- 研究紹介
- 外国にルーツをもつ人々といかに共生するかという問題は、現代社会の大きな課題のひとつです。近世のフランス王国でも、戦争の勃発、政治宗教的な迫害、国際商業の発展、旅行文化の誕生を背景として、外国人の到来と定着がみられました。彼らを統合ないし抑圧・差別する法・制度や言説がどのように形成され展開したのかを観察することで、歴史学の立場から現代社会が直面する課題を考察するための素材を提供できると考えています。
- メッセージ
- 修士1年の終わりに、パリの国立公文書館で18世紀の手稿文書を初めて手にしたときの高揚感を今でもよく覚えています。近世フランスという「過去」に直接触れたような感覚を抱いた瞬間でした。史料と虚心坦懐に向き合うなかで、過去の社会がいかに現代社会とは異なる秩序や規範によって支えられていたかを実感することが何度もありました。こうした実感は、自分たちの社会や時代を相対化し、異なる文化や慣習のなかで生きる人々への想像力を育んでくれます。皆さんも大学院での学びを通して過去と対話してみませんか。
- 主要業績
- 「近世フランス植民地における外国人の法的地位―アンティル諸島への外国人遺産取得権の導入から廃止まで―」『歴史学研究』993号(2020);「18世紀フランスにおける外国人遺産取得権―パリ・サン=ジェルマン=デ=プレ地区の事例から―」『史学雑誌』127編9号(2018年);「18世紀フランスにおける外国人と帰化 : ブリテン諸島出身者の事例から」『史学雑誌』123編1号(2014年)。
- 概説・一般書
2023年 1月更新