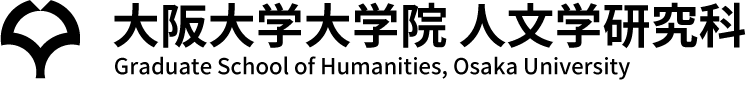人文地理学講座の開設は1995年であるが、それ以前の日本学比較文化学講座時代から研究・教育の蓄積があり、とくに古地図研究、歴史地理学の領域で大きな成果をあげてきた。現在の講座担当教員は堤研二教授と佐藤廉也教授である。堤教授は、人口流出地域の社会と経済の変動を分析し、欧米の研究者たちとも交流を行ってきた。佐藤教授は、アフリカ・アジアを中心にフィールドワークを実践し、焼畑・狩猟・採集など環境利用型の生業活動の研究を行ってきた。これまで人文地理学が蓄積してきた理論や手法を確実に身につけるとともに、関連分野の方法論の検討や摂取にも関心を広げたい。このことは、拡大が著しい現代の人文地理学の研究フロンティアの理解とともに、将来さらに盛んになる学際的研究への参加においても役立つであろう。
教員紹介
教授 佐藤 廉也
 さとう れんや さとう れんや1967年東京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程(地理学専修)中退。博士(文学)(京都大学、1999年)。京都大学総合博物館助手、九州大学大学院比較社会文化研究院助教授(准教授)を経て、2015年4月より現職。 専攻:人文地理学 |
- 研究紹介
- アフリカ(熱帯林・サバンナ)、中国内陸部(半乾燥地)、ラオス(熱帯モンスーン)などでフィールド調査を続けながら、資源利用や人類の環境適応の諸問題について研究しています。進行中の主な研究テーマは、生業と環境適応に関する研究(とくに焼畑農耕、採集・狩猟活動)、空中写真や地形図などの地理情報を用いた土地利用・集落動態研究、ヒトの出生・死亡と人口動態に関する研究、環境利用・認知に関する研究などです。いずれも人類の環境適応の観点から、文化の地域性と普遍性を解明することをめざしています。
- メッセージ
- 地理学では様々な専門分野にまたがる横断的研究が求められ、「ブリッジ・サイエンス」とよばれることもあります。地理学を学ぶ上で大事なことは、世界に対する好奇心と、それを科学的に説明したいという欲求です。そして何より大切なのは、「研究を楽しむこと」「楽しくて仕方がない研究テーマを選ぶこと」です。自分で楽しくないのに人を面白がらせるような研究ができるわけがない、というのが私の持論です(卒論レベルの研究であっても同じです)。世界の謎を解いていく楽しさを皆さんと共有したいと考えています。
- 主要業績
- 『イモとヒト 人類の生存を支えた根栽農耕─その起源と展開』平凡社(共著、2003);「アフリカのハチミツ酒:醸造技術と飲酒文化」日本醸造協会誌99(2004);『朝倉世界地理講座─大地と人間の物語─11巻 アフリカI』『同12巻 アフリカII』朝倉書店(共編著、2008);『ネイチャー・アンド・ソサエティ研究 第3巻 身体と生存の文化生態』海青社(共編著、2014);「エチオピア南西部の森林農耕民マジャンギルの植物利用と認知」地球社会統合科学1(2014)
- 概説・一般書
- 「森の民マジャン:自然の要塞としての森」季刊民族学109(2004);『講座ファースト・ピープルズ第5巻』明石書店(共著、2008);『グローバル化時代の人文地理学』放送大学教育振興会(共著、2012);人文地理学会編『人文地理学事典』丸善出版(共著、2013);日本アフリカ学会(編)『アフリカ学事典』昭和堂(共著、2014);高等学校地理歴史科用文部科学省検定済教科書『地理B』東京書籍(共著、2014)
2018年 8月更新
教授 大呂 興平
 おおろ こうへい おおろ こうへい1976年鳥取県生まれ.東京大学教養学部卒業.東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了.農林水産省中国農業試験場(現 農研機構 西日本農研)研究員,シドニー大学客員研究員,大分大学経済学部准教授等を経て,2024年より現職.博士(学術)(東京大学2011年). 専攻:人文地理学 |
- 研究紹介
- 日本や諸外国における農業や食料貿易の変動を、産業を構成する個々の主体(世帯群や企業群、政府や消費者)の行動に注目して精緻かつ体系的に説明することを目指しています。具体的には、日本の国土周辺部における肉用牛生産の拡大や、オーストラリアにおける wagyu 産業の勃興、日本の食糧調達と南太平洋地域の変動などを主な研究対象としてきました。フィールドワークにより、変動の背後にある主体の対応を捉えることを通じて、現象のメカニズムやその地域社会における含意を深く理解したいと考えています。
- メッセージ
- 自分の知らない場所に身を置き、見て、歩いて、人々の話に耳を傾けながら、目の前で起きている現象やその場所について考える。こうした試みは、外から見ているだけでは捉えられない貴重な知見を導き出せる本質的に重要な知的作業ですが、そんな理屈を抜きにしても、とても刺激的で楽しいものです。フィールドワークだからこそ得られるかけがえのない経験を、皆さんと分かち合いたいと思っています。ともに現場を歩き、ともに語り、ともに考えましょう!
- 主要業績
- 『日本の肉用牛繁殖経営ー国土周辺部における成長メカニズム』農林統計協会(2014);「沖縄・多良間島における肉用牛繁殖経営群の動態」『地理学評論』94(2021);「トンガのカボチャ産業-世界経済の縁辺から」『地理の研究』194(2016);「EUにおける牛肉貿易と輸入管理制度」『畜産の研究』69(2015);「オーストラリアにおけるwagyu産業の展開」,人文地理 64(2012);The evolution of global value chains: An explanation of the displacement of captive upstream investment in the Australia-Japan beef trade, Journal of Economic Geography (2011,共著))
- 概説・一般書
- 文部科学省検定済教科書『高等学校 新地理総合』帝国書院(共著,2021);文部科学省検定済教科書『中学生の地理』帝国書院(共著,2020);『食と農のフィールドワーク入門』昭和堂(共著,2019);『牛ET実践手引書』東京図書出版(共著,2022);『漁に生きるー姫島漁業の模索』佐伯印刷(2018);「肉用牛経営の飼料自給はなぜ進まないのか?」『農村と都市をむすぶ』72(2023);「イギリス・スペインwagyu見聞録」『肉牛ジャーナル』32(2019);「超大型肉用牛繁殖経営の出現ー成立過程と技術的基盤」『畜産の情報』340(2018)
2025年 4月更新